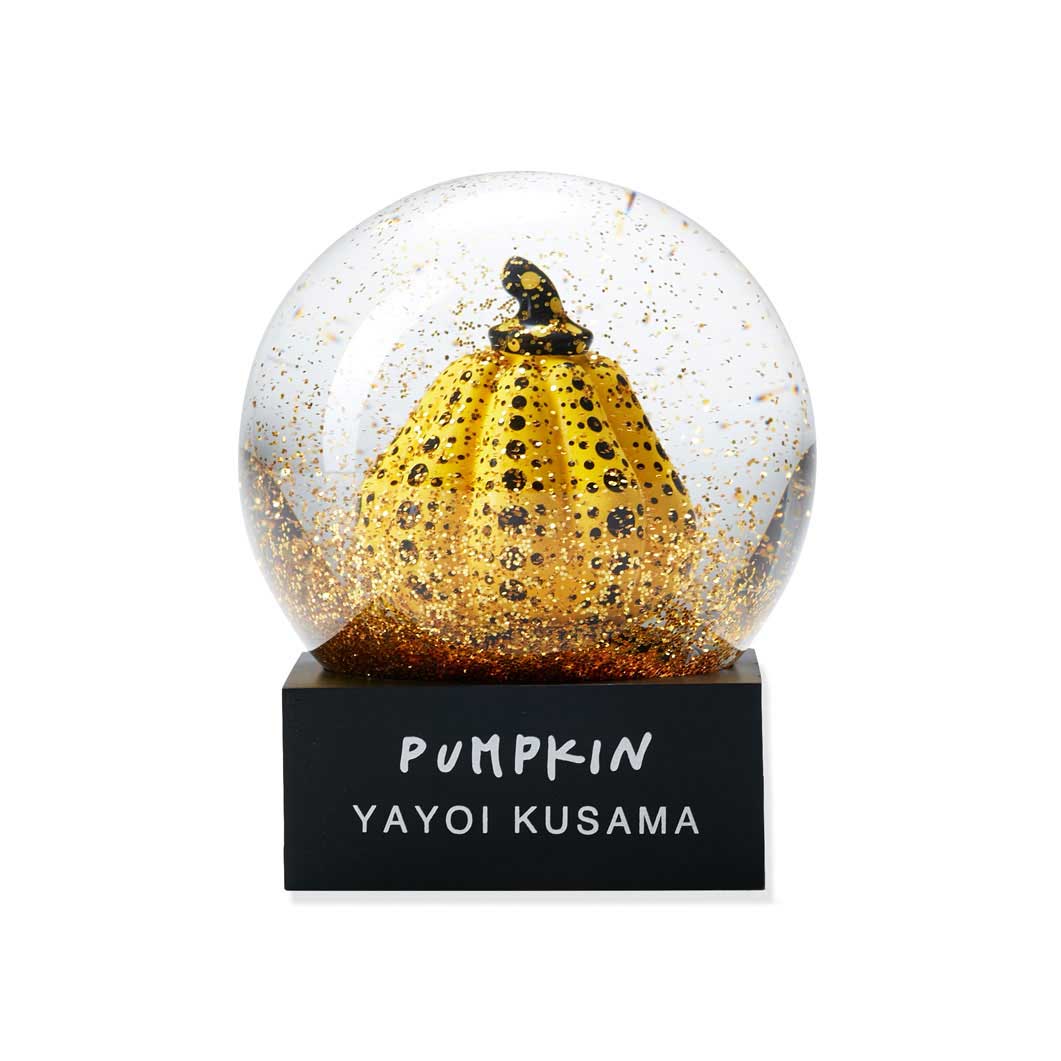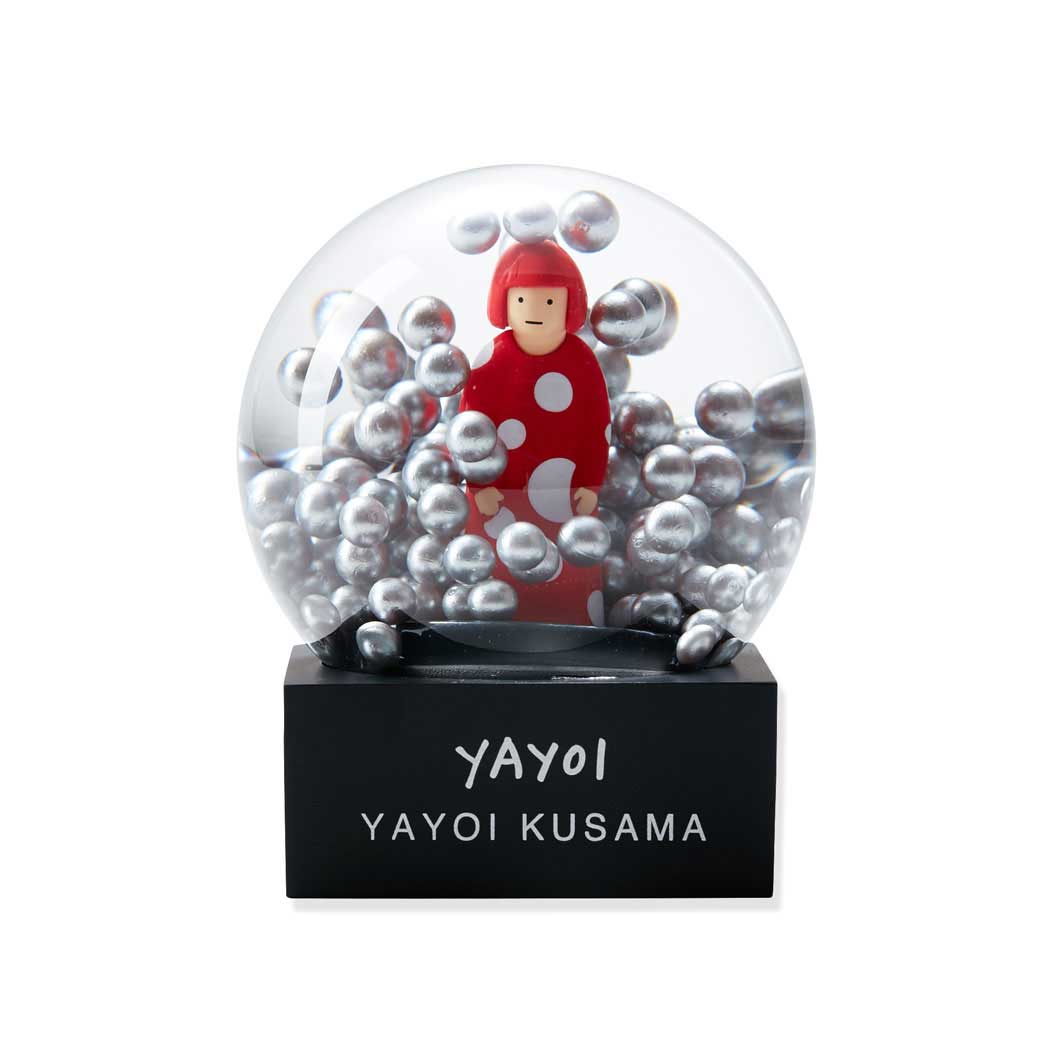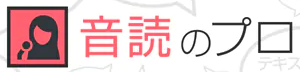―PR―
『魂の文章術』(ナタリー・ゴールドバーグ著、小谷啓子訳)
| タイトル |
|---|
| 魂の文章術―書くことから始めよう |
ここでは、ナタリー・ゴールドバーグ氏によります『魂の文章術』のご紹介をします。
ゴールドバーグ氏は、アメリカで創作クラスの講師をされている詩人&作家です。
本書は、アメリカで100万部を売上げ、世界12ヶ国以上で翻訳出版されているというミリオンセラーの作家指南書です。本書には「魂の文章術」というタイトルが付されていますが、正確に言うと、通常の意味での文章術に関する指南書ではありません。
本書の原題は「Writing Down the Bones」となっていますので、内容を踏まえてその意味するところを考えてみると、「心の奥底から湧き上がってくる思いを書き留めよう」という感じでしょうか。
従いまして、本書ではテクニック的な内容が事細かに記されているわけでありません。ここでは、著者の“書くこと”に対する熱き思いがエッセイ風にまとめられています。逆に言えば、だからこそ著者の“書くこと”に対する情熱が読者に伝わり、国を越えて世界的に愛される作品になったのでしょう。
『魂の文章術』の概要
では、具体的にその内容の一部をご紹介しましょう。
文章修行の基本は、制限時間を決めて行う練習だと著者は断言します。この際、時間の長短は大した問題ではなく、大切なことは、いかに書くことに集中するか、ということです。
そして、書く際のルールとして次のポイントを挙げています。ここで、その箇所を引用しておきましょう。(p13~14)
- 手を動かしつづける
手をとめて書いた文章を読み返さないこと。時間の無駄だし、なによりもそれは書く行為をコントロールすることになるからだ。 - 書いたものを消さない
それでは書きながら編集していることになる。たとえ文章が不本意なものでも、そのままにしておく。 - 綴りや、句読点、文法などを気にしない
文章のレイアウトも気にする必要はない。 - コントロールをゆるめる
- 考えない。論理的にならない
- 急所を攻める
書いている最中に、むき出しの何かこわいものが心に浮かんできたら、まっすぐそれに飛びつくこと。そこにはきっとエネルギーがたくさん潜んでいる。
要するに、著者は頭で考えて文章を書くな、といっているわけです。もっともっと心の奥底から湧き上がってくる思いを言葉にしなさいということです。こうした姿勢は、著者の次の言葉を踏まえておくとその意味が良く分かります。
ものを書くときに、自分の中の“創造者”と“編集者”(内なる検閲官)を切り離し、創造者がのびのびと呼吸し、探求や表現ができるようなスペースを作ることがたいせつだ。(p40)
こうしてみると、著者が本書で言わんとするところが何となく分かってきます。私たちは、何かを書こうとするとき、素晴らしい作品を書こうとか、感動的なストーリーにしようとか、美しい言葉を使おうとか、ついつい余計なことを考えてしまいます。しかし、こうした考え自体が文章からその生命を奪ってしまうことになるようです。
本書を読んでいると、何でもいいからとにかく文章を書きたくなってくるから不思議です。スランプに陥り、何も書けなくなってしまった時など、最適の書物かもしれません。
文章修行に関する具体的なアドバイスとしては、次のようなポイントが指摘されています。
「いざ机に向ったとき、何を書こうかとあまり時間をかけて考えてはいけない。そんなことをしていると、余計に書けなくなってしまう」といいます。そんな時のためにも、日頃から自分のテーマリストを作っておくことを勧めています。本書では、テーマを考えるためのヒントも数多く紹介されています。
さらに、自分独自のオリジナルなディテールを使うことが重要だと述べられています。かつて訪れた店や招待された結婚式など、その場面のディテール(詳細)をよく観察し、作品の中に移植するというわけです。
文章にディテールを盛り込むことによって、自分が感じたエクスタシーや悲しみをもっと上手に伝えることができるようになるといいます。
そして、文章の達人になりたいなら次の三つのことが必要だと言います。つまり、たくさん読むこと、真剣によく聞くこと、たくさん書くことです。
文章についての格言に「語るより見せろ」というものがありますが、これについても著者は説明しています。「怒り」を例に考えてみると、自分が怒っているということを書くのではなく、自分を怒らせているものを具体的に示すことによって、読者に同じ感情をもたらしなさい、ということです。
ところで、毎日規則正しく書いているのに少しも文章が上達しないという人がいます。そういう人の問題点は、いい子ブリッ子の生き方をしている点だといいます。その気もないのに、ただ従順に書いているだけだというわけです。そんな時は、本当に書きたくなるまでしばらく書かない方がいいんだ、と言います。
日本の禅を学び、瞑想を習慣としている著者が、独自の文章論を展開する一風変わった作家指南書だと言えるでしょう。静かな情熱が湧き上がってくる神秘的な書物でもあります。